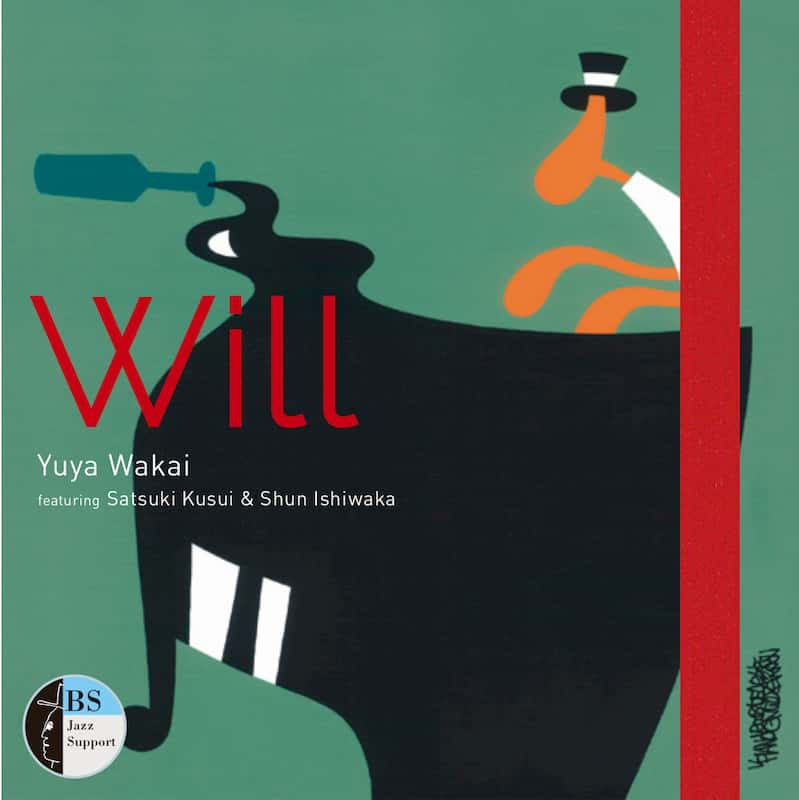
- Étude Op.10 No.6 (9:45)
- Spring Has Sprung With A Little Melancholy (9:46)
- Children's Play Song (9:32)
- Bolivia (9:48)
- Is That So? (6:37)
- Will: Part 1, Part 2 (9:30)
- Will: Part 3 (5:49)
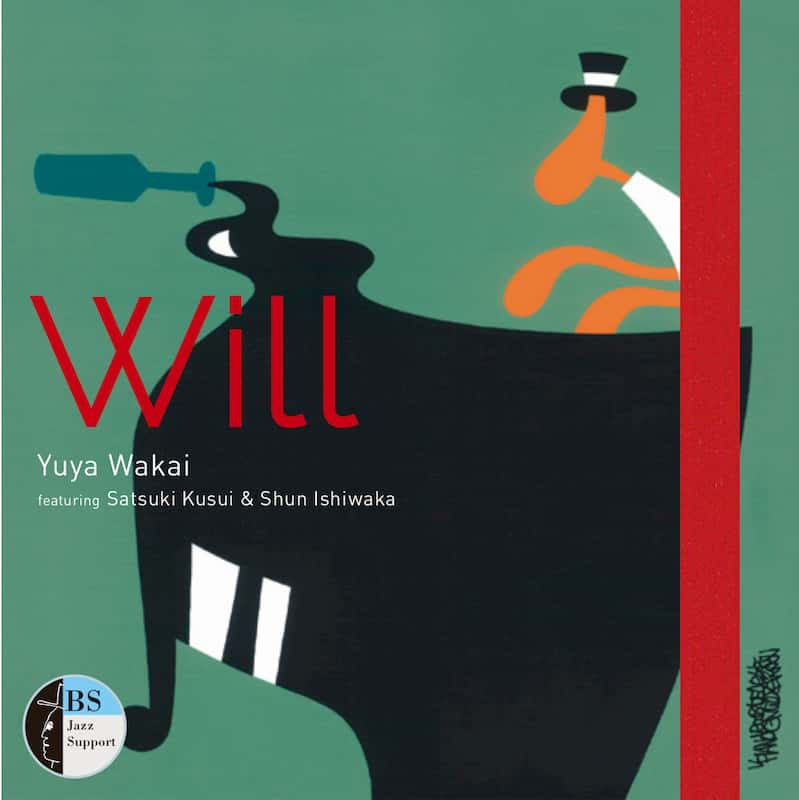
Piano

1986年、愛知県名古屋市生まれ。3歳よりヤマハ音楽教室に通い、ピアノを村上由里子氏、作曲・和声学を若林千春氏に師事。大学入学と同時にジャズ研究会に所属し、都内のライブハウスに通いながら独学でジャズピアノを学ぶ。2005年第36回山野ビッグバンドジャズコンテストに慶應義塾大学ライトミュージックソサエティの一員として出演し、バンドで優秀賞、個人で優秀ソリスト賞を受賞。これまでに6枚のアルバム「しあわせな森のジブリ」( 2010 年)「しあわせな夢のジブリ」「PianoでJazz !!」(2011年)「Piano Jazz The Beatles」(2012年)「Images」(2013年)「神曲Jazz」(2014年)のプロデュースを手掛け多方面から大きく評価される。2011年青木カレン(vo)とともにNHK教育テレビ(Eテレ)「3ヶ月トピック英会話・歌って発音マスター!~魅惑のスタンダード・ジャズ編~ 」にレギュラー出演。2013年同じくNHK教育テレビ(Eテレ)「囲碁フォーカス」にて大きく特集され反響を呼ぶ。現在ライブ・レコーディングなど様々なシーンで幅広く活躍中。教育活動にも力を注いでいる。趣味は囲碁と数学。
Bass

1985年、北海道旭川市生まれ。幼少期にエレクトーン、中学からエレキベース、法政大学からコントラバスを弾き始める。井上陽介に師事し在学中よりプロとして活動。2011年より辛島文雄トリオに参加し全国ツアー。現在、TOKU、谷口英治、グレース・マーヤ、若井優也、魚返明未のバンドを始め海外ミュージシャンの来日公演のサポートも数多く務める。ジャズの伝統に根差した強靭なスウィングビートと、様々なジャンルに対応する幅広い音楽性を持っている。仲間からは「歩くジャズ辞典」と言われるほどジャズに造詣が深い。
Drums

1992年、北海道札幌市生まれ。4歳からピアノ5歳でドラム、13歳でジュニアジャズスクールに通い本格的にドラム演奏開始。15歳にして日野皓正(tp)バンドに抜擢される。東京芸大付属高校を経て同大学打楽器科へ進学し打楽器科を首席で卒業。在学中よりファーストコール・ドラマーとして数々のバンドのレコーディングやライブに参加。天才ドラマーとして、また作曲家としても話題となる。2015年12月初のフル・リーダー作「Cleanup」を発表し多方面から高い評価を得る。2016年6月ブルーノート東京にて自己のトリオでカート・ローゼンウィンケル(g)と出演。ビッグネームとの共演歴はすでに枚挙に暇がなく、いま最も注目されているドラマーといえる。
音楽評論家 中川ヨウ/Yo Nakagawa
美しいアルバムが誕生した。『Will』と名付けられたこの作品は、ジャズ・ピアニスト、若井優也が初めてその全貌を見せた、リマーカブルなアルバムである。
その美しさは、どこから来たものなのか。若井の内面から。人間として成長した彼の内には、大きな優しさと思慮深さがある。後者はたまに「人前でピアノを弾く仕事」の邪魔をすることがあるかもしれないが、その内面の全てが彼をここまで導いてきた。そして、3歳からヤマハ音楽教室に通った、生涯をかけたピアノへの献身から。更に、「ピアニストになりたかったが、数学者にもなりたかった」と彼が語る数学への愛からも。古代ギリシャで音の協和を説いたピタゴラスや、「ハルモニア原論」を著したアリストクセノスを持ち出すまでもなく、古来音楽と数学は切っても切れない関係にあり、また議論の対象にもなってきた。
こうして『Will』というアルバムを手にした今は、彼のこれまでの道全てが必要なものであったと思えるのだ。
若井優也は、1986年1月14日に愛知県名古屋市に生まれた。幼い頃から才能を発揮したが、ジャズに本格的に取り組むのは東京大学に入学し、ジャズ研究会に入ってからだと言っていい。都内のライヴハウスやセッションに通い、独学でジャズを学んだ。筆者はその頃、初めて彼のピアノを聴いている。2005年(第36回)山野ビッグバンド・ジャズ・コンテストに、慶應義塾大学ライト・ミュージック・ソサイェティのピアニストとして出場し、ライトを2位に、そしてご本人は個人で優秀ソリスト賞を受賞した。
その演奏ですぐに気になるピアニストの一人になったが、その後間をおかずに高樹レイ、大野えり、青木カレンといったシンガーたちのアルバムやライヴに参加するようになり、次に筆者が彼の演奏を生で聴いたのは、伊藤君子のピアニストとして青山のBODY & SOULに出演した時だった。その頃増えてきたバークリー音楽大学卒業者とは異なるコード進行とテイストをもっており、彼のピアノに少なからず興奮したのをよく覚えている。
リーダー・アルバムは、2010年のジブリ映画の楽曲をカヴァーした『しあわせな森のジブリ』がデビュー作となったが、“幸せな”と言うよりは、哲学的でもあり、深い森のラビリンスにいざなうようなそのピアノにかえって膝を打ったのだった。以降、総計6作を発表してきたが、ライヴで感じる“若井優也らしさ”がひしひしと伝わってきたのは今作が初めてになる。
オリジナリティというものは簡単に獲得できるものではなく、オリンピックに出場して金メダルをとるようなものだ。そのオリジナリティを、若井優也がこの『Will』で強く感じさせたことを心から喜ぶと共に、高く評価したい。インタビューで彼にそう告げると、若井はそれぞれの名前を挙げて、トリオ・メンバーの貢献度の高さを語った。
「楠井五月くんとは、大学生の時からよく知っている仲です。当時から天才肌で、ベーシストとして群を抜いていました。プロとして活動を始め、久しぶりにジャム・セッションで再会した時に改めて感動し、いつか一緒にやりたいと話していたのが実現し、ここ2~3年このトリオでご一緒しています。石若駿くんと初めて会ったのは、彼が芸高(東京芸術大学付属高校)の時でした。とんでもないドラマーが出てきたなと思いましたが、それから間もなく日野皓正グループに抜擢され、すぐにメジャーになり、以来ずっと多忙を極めています。このトリオでもドラマー以上の存在で、叩くというより音楽を奏でてくれる。パーカッシヴな側面ももちろんありますが、さまざまな音色を生み出し、絵画的でもあるのです」
音楽がどう進んでも受け入れてくれるこの2人がいたから、自身のピアノも許容量を増したと、若井は語った。
ここで、若井優也自身の言葉を借りながら、簡単に収録された楽曲の解説をしたい。封印していたクラシックを、最近また弾くようになったという彼。冒頭は、「ショパンのエチュードから、ロマンチシズムに惹かれる6番を演奏しました」。2曲目は、楠井作曲の〈Spring Has Sprung With A Little Melancholy〉で、「作曲の技法としてサイコロを振りながらランダムに曲を書き、途中まで進んだら鏡写しにして作曲を進めたそうです」。どう完成させるかが命だろうが、そこに楠井の生命を感じ、明るいけれどどこか謎がある空気感が好きだと若井が語った。ビル・エヴァンス作曲の〈Childrens’ Play Song〉は、「子供でも鼻歌で歌える素朴な曲。テーマを弾いたらフリーに移行し、何も決めないで演奏しました」。作曲とインスピレーションが見事なバランスで混じり合った、素晴らしいソロ・ピアノになった。
「シダー・ウォルトンはぼくにとって特別な存在で、〈Bolivia〉はジャム・セッションでよくやっていた曲です。めちゃくちゃになってもいいから、3人で楽しく演奏しました」。若井と楠井のデュオによる〈Is That So?〉は、デューク・ピアソンの曲。「デュオだからいつもとは違うやり方でやりたいと、楠井くんには半ばベース・ソロのように弾いてもらいました」。若井のピアノが実に自由で面白い。
最終曲は、抽象的なタイトルにしようと〈Will〉と名付けられた組曲だが、若井のピアノにみなぎる意志を反映し、非常にふさわしいタイトルになった。パート1は、これまでもタイトルなくトリオで演奏されることがあったが、美しい構築力があるテイクだ。パート3が、若井が夫人と洞爺湖に旅行をした時に書いた曲で、帰郷しすぐに演奏したという。そしてパート2は、その2曲の橋渡しになっており、ソロ・ピアノでパート3の石若駿のドラムスへとバトンが渡される。人間的な美しさから始まり、最終的に壮大な自然の美しさを前に頭を垂れる、そんな若井の精神が描かれている。
素晴らしいアルバムが出来たと思う。本作を通過点とし、若井優也も、楠井五月も、石若駿も更に前へと進むことだろう。その先にどんな景色が広がっているか、ちょっと想像もつかないのだけれど、また一緒に見られることを信じて、リリース・ライヴに足を運び、これからもBODY & SOULでこのトリオを聴き続けたいと思っている。(2019年4月記)